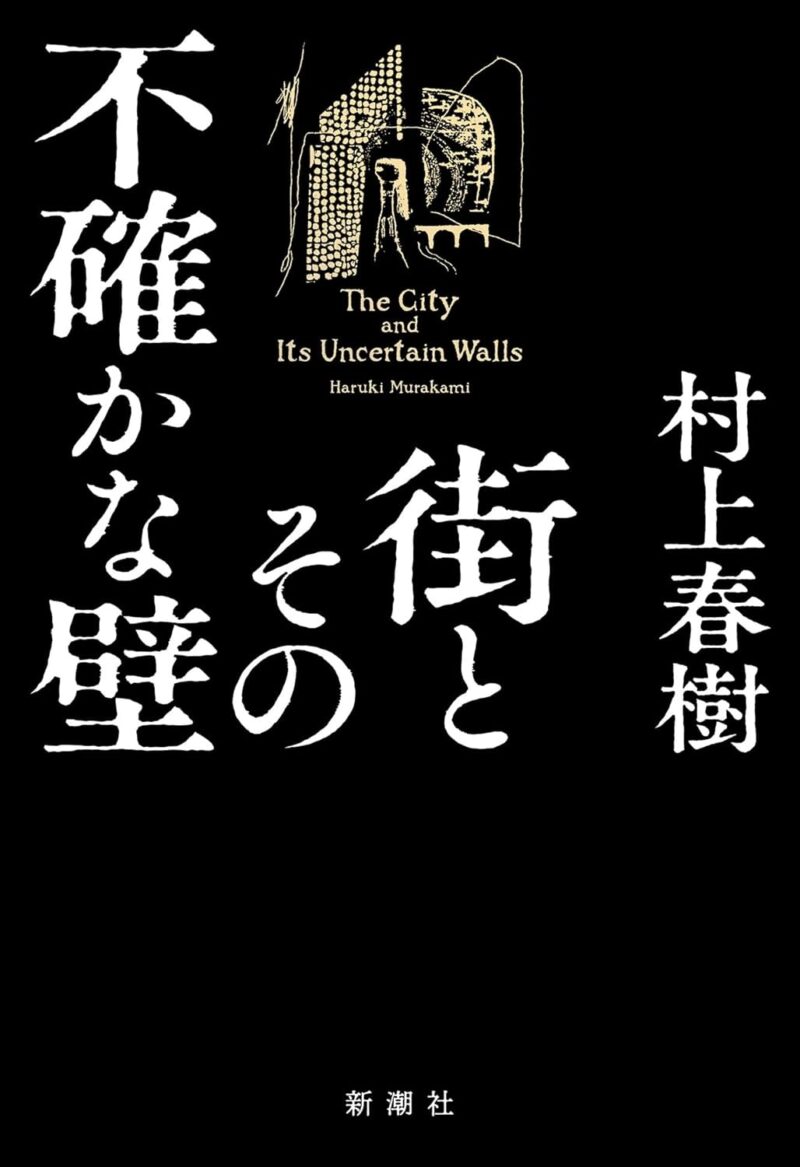三島由紀夫の『豊饒の海』や、伊集院静の『愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない』のような、作家の歩みや世界観を総括する位置づけの作品だと、私は勝手に思っている。
村上春樹の武器は、隠喩力、描写力、想像力、幻想力、そして物語る力。それらが惜しみなく発揮されていると感じる。まさに「村上ワールド」の真骨頂であり、集大成といっても過言ではないだろう。もしかすると、これが最後の大作になる可能性さえある——もちろん、私は次の大作を心待ちにしているのだが。
村上春樹の作品には、真っ白なキャンバスに、脳が生み出した言葉や文章を紡ぎ、一枚の絵を描き出していくような印象がある。まさに無から有を生み出す作業だ。何もないところに言葉と文章を積み重ね、それらを巧みに統合することで、ひとつの作品として微妙なハーモニーを奏でていく。
「その言葉とこの言葉を結びつけるなんて無理では?」と思わせるような組み合わせを成立させたり、「この隠喩はどういう意味なのだろう」と首をかしげながらも、なぜか腑に落ちてしまったりする。また、「この表現はギリギリすぎるのでは」と感じるような冒険にも、ためらいなく踏み込んでくる。
読者は、現実と非現実のあいだを行き来することになる。そして読後には、なんともいえない不思議で心地よい感覚が残る——まさに、脳で味わう作品だ。